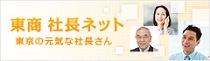第23回 社員の辞めない教育・研修
第23回 社員の辞めない教育・研修 2014・4・10
外食経営塾塾長 今津久雄
「顧客目線 3」
私は、飲食業40年経験しましたが、ほとんどが「非日常」型店舗でした。別名「驚かせ産業」とも言っていました(私以外にも某個性的高級飲食店(八王子から東京タワー近く他、経営譲渡されました)経営者もおっしゃっていました。それには「家庭にない専門性」「店造り」(雰囲気)が大きな特徴です。私の父が創業時、母体の旅館の支店からスタートしましたから、旅館風店づくりが当たり前の発想がお客様には「驚き」だったのだと思います。当時高度成長期でしたから・・・そして30年経過してからは「大型店受難」の時期になります。また、飽食の時代的影響もあり「お客様のプロ化」で知識や感性も豊かになられ、飽きも早く二極化的になっているのが今日ですね。
先日某有名料亭にお邪魔しました。「メニュー数を豊富に10数品目の料理」を出して高級食材を使って・・・何か今一つ工夫を感じられませんでした(会費30000円 60余品目の食材使用とか)その一つにフカヒレにすっぽんにアワビが一緒になったスープ仕立てのものは他ではできないとは思いましたが・・・???味が邪魔しあっていたようにも感じました。
次に「非日常」型は「来店機会」が狭められるということが大きな特徴の一つになりますから、需要供給のバランスで「高価格」になりがちですが、ここにヒントがあるように思います。今までは新鮮高級食材をふんだんに使用するから原価が上がる・・・回転率を考えてつい、使いまわし(船場某有名料亭)と、もってのほかの行為に走ってしまうようなところも出てきてしまうのでしょう。決して高価格だから楽ではないのですね。つまり・・・メニューの個性化・・・商材供給ルートの開拓開発・・・が大きな要因になるということです。(周知の事実でしょうけれど)また、効率化のためにセントラルキッチン的動きに走りやすいのですが非日常型はあまり功を奏した例がないように思います(しかし、今は肉類は可能になってきているかもしれませんね)どちらかというと、調理師の腕にこだわるところの影響の方が大きいかもしれません。それと日本の特徴「素材の味を生かす」ということではないでしょうか!非日常型にもいろいろありますね。気をてらったりして一時は反響を得ても恒久的には経営できません・・・その方法は・・・
- Posted by
 Co57
Co57 - Posted in 57の会 活動報告
 7月, 07, 2014
7月, 07, 2014 No Comments.
No Comments.
News
- 第153回 「今津久雄的こころ」 令和 7年4月10日 外食経営塾塾長 今津久雄 2025/04/15
- 57の会 FAX通信 vol.199 2025年3月20日 (株)コミュニケーションオフィス57 代表取締役 今津久雄 2025/03/25
- 第152回 「今津久雄的こころ」 令和 7年3月10日 外食経営塾塾長 今津久雄 2025/03/14
- 57の会 FAX通信 vol.198 2025年2月20日 (株)コミュニケーションオフィス57 代表取締役 今津久雄 2025/02/25
- 第151回 「今津久雄的こころ」 令和 7年2月10日 外食経営塾塾長 今津久雄 2025/02/15
- 57の会 FAX通信 vol.197 2025年1月20日 (株)コミュニケーションオフィス57 代表取締役 今津久雄 2025/01/25
- 第150回 「今津久雄的こころ」 令和 7年1月10日 外食経営塾塾長 今津久雄 2025/01/15
- 57の会 FAX通信 vol.196 2024年12月20日 (株)コミュニケーションオフィス57 代表取締役 今津久雄 2024/12/25

 03-5604-0020
03-5604-0020